学生から大人までニーズの高いルーズリーフ。
ルーズリーフはノートと違って、使いたい枚数を自由に使うことができたり配置も自由に選べて便利ですよね。
また、1枚ずつ使用するので作業スペースをとることもなく、端から端まで書くことができます。

でもルーズリーフって、保管方法が難しいよね…
ルーズリーフはノートのようにまとまっていないので、バラバラになりやすいという欠点があります。
せっかくまとめたのにバラバラになってしまったら最悪の気分になりますよね。
そこで今回は、そんなルーズリーフの保管方法について詳しく解説していきます!
これを読めば以下の内容が分かります。
- 使用前のルーズリーフの保管方法
- 使用後のルーズリーフの保管方法
- ルーズリーフの長期保管方法は製本がおすすめの理由
順番に見ていきましょう!
使用前のルーズリーフの保管方法おすすめ3選!

使用前のルーズリーフを袋に入った状態のまま持ち運んでいるという方も多いかと思います。
しかし、このようなストレスはありませんか?
- 袋を開ける音がうるさい
- 袋の粘着が弱くなってくる
- 1枚ずつ取り出しにくい
- 出しすぎたときに戻しにくい
- 枚数が少なくなったらシワになりやすい
特にルーズリーフの袋を開ける音は、私も学生の頃からストレスでした。

静かな空間にビリビリッという音が響き渡ると、周囲の目が気になるよね…
図書館などの静かな空間で作業する際には、音は気になるポイントですよね。
かといって少しずつ開けようとしても、ビリビリビリビリッと音がゆっくり続くだけです(笑)
粘着が弱くなってきたら音もしなくなりますが、中身が出てきてしまう心配があります。
また、1枚ずつ取り出しづらいというのも欠点の1つです。
スーパーの袋と同じように、手が乾燥していると取るまでに時間がかかってしまいます。
多く出しすぎてしまって袋に戻そうと思っても、なかなか戻せません。
時間がかかってしまうと、焦ったりイライラしたりしてしまうものですよね。
袋の中が残りわずかになるとカバンの中でシワになっていることもあり、使う気が失せてしまいます。
しかし、管理方法1つでこのようなストレスとおさらばすることができるのです!
これから使用前のルーズリーフの保管方法を3つご紹介します。
ルーズリーフケース
まずおすすめするのが、ルーズリーフケースでの保管方法です。
ルーズリーフケースといっても、どんなものかピンとこないという方もいるかもしれません。
私も学生の頃にはその存在を知らずに、使ったことはありませんでした。
ルーズリーフケースとは、ルーズリーフを傷めずに綺麗に保管するための専用の入れ物です。
封筒のような形をしており、デザインも豊富です。
ネット通販では、可愛いデザインのケースも多く揃っており、見ているだけで欲しくなります!
ルーズリーフケースの留め具はボタンのものが多く、開けるときの音も気になりません。
1枚ずつ取り出しにくいというストレスも、ルーズリーフケースを使用すれば解消されます。
また素材もしっかりしているので、雨の日も安心して持ち運ぶことができます。
クリアファイル
コストをなるべく抑えたいという方は、クリアファイルでの保管方法がおすすめです。
家にあるクリアファイルを使えば、お金をかけずに済みます。
購入したとしても、100均やコンビニで安く手に入るのでコストを抑えることができます。
クリアファイルは薄くて場所をとらない点もメリットの1つです。
しかし、クリアファイルで保管する場合、隙間からルーズリーフが出てしまう可能性があります。
そうなると、カバンの中でぐちゃぐちゃになってしまいます。
そんなリスクを抑えるために、クリアファイルの上をクリップでとめておくなどの工夫をしておくと安心です。
クリップボード
クリップボードに使う枚数だけルーズリーフを挟んで持ち歩く方法です。
クリップボードは二つ折りのものやポケット付きのものなど、様々な種類やデザインがあります。
最近では100均でも様々なクリップボードを販売しているので、安く買うことも可能です。
デザインや機能性を求める場合は、ネット通販や文房具店などで購入するのが良いかもしれません。
クリップボードは下敷き替わりにもなりますので、机の無い場所でもそのまま字が書けるというメリットがあります。
説明会や野外活動でルーズリーフを使用する際は非常に便利です。
二つ折りのクリップボードであれば、ルーズリーフを保護することもできます。
しかし、全面が守られているわけではないので、雨の日には注意が必要です。
使用後のルーズリーフの保管方法はバインダー以外にもある?
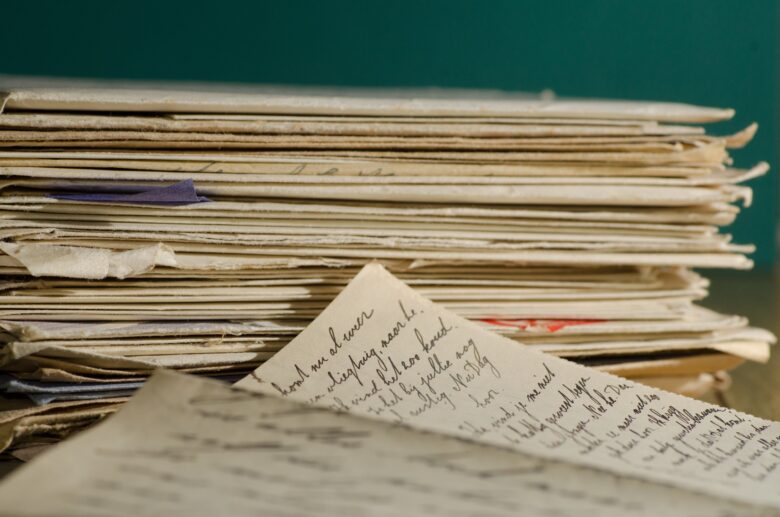
せっかく綺麗にまとめたルーズリーフを、どこに保管するかというのは悩みどころですよね。
持ち運んでいる間にバラバラになったり、なくしてしまったりしたらルーズリーフを使う意味もなくなってしまいます。
ここでは使用後のルーズリーフの保管方法について、定番のバインダーからそれ以外の方法までご紹介していきます。
ルーズリーフバインダー
使用後のルーズリーフの保管にルーズリーフバインダーを使用している方は多いかと思います。
ルーズリーフバインダーは、インデックスシートで区切ることができるというメリットがあります。
学生さんは教科や講義ごとに区切ることができて、非常に便利です。
私はノートを使用する際、書く内容を最初に決めても途中で違う内容を書きたくなってしまうことが多々あります。
困ったことに、違う内容を書くとしたら、新しいノートに変えたいと思ってしまいます。
そうなったらノートが無駄になってしまい、使わないノートが溜まりがちです(笑)
そんな私にはルーズリーフがピッタリなのです!
ルーズリーフバインダーを使えば、インデックスシートで内容ごとに区切ることもできて配置も自由に変えることができます。
デザインも豊富なので、形から入るタイプの私には嬉しいポイントです。
しかし、デザインや機能性を求めると値段が高くなるのがデメリットです。
ルーズリーフを保管するのにあまりお金をかけたくないという方や、ルーズリーフをたくさん使用するという方にはあまり向いていません。
ルーズリーフをたくさん使用する場合、当然バインダーの数も多く購入しなければならないためお金もかかってしまいます。
そのような方は別の方法を試してみて、自分にピッタリの保管方法を探ってみるのがおすすめです!
ペーパーファスナー
ペーパーファスナーはネット通販や100均などで安価に手に入れることができます。
1袋に何個も入っているタイプのものが多く、コスパが良いです。
ルーズリーフを綴じる際は、2つの穴に通すだけなので簡単に綴じることができます。
しかし、表紙やカバーが付いているわけではないので、長期保管には向いていないです。
しかし、一日分や講義ごとといったような一時保管には最適な方法だと言えます。
封筒
ルーズリーフを封筒に入れて保管するという方法もあります。
封筒も100均やコンビニなどで安く手に入れることができますよね!
使用したルーズリーフを内容ごとに分けて封筒に入れるだけなので、手間もかかりません。
しかし、中身が見えないというデメリットが存在します。
特に同じ色の封筒で保管してしまうと、一体どの封筒に何が入っているのか分からなくなります。
書類を探しているときに、いちいち封筒から出して探すのはイライラしてしまいそうですよね。
そして何故かそういうときに限って見つからないものです(笑)
そんなときの対処法として、入っている書類の内容を封筒に記しておくのがおすすめです。
また、窓付きの封筒を使用してみるのも良いでしょう。
一度試してみてはいかがでしょうか?
ルーズリーフリング
ルーズリーフリングには、数か所とめるタイプから、すべての穴をとめるタイプのものまであります。
すべての穴に通すのが面倒だという方には、数か所をとめるタイプがおすすめです。
様々な色がセットになったものや、切れるタイプのものも売っていますので、自分なりに組み合わせてみるとオシャレに保管することができます。
しかし、綴じる枚数が少ないとリングがかさばってしまって保管しにくいことや、本棚にしまいにくいといったデメリットがあります。
ある程度の枚数があって一時保管する場合などは、最適な保管方法かと思います。
ネット通販では様々なルーズリーフリングを見ることができるので、気になる方は一度チェックしてみてくださいね!
スライドバーファイル
綴じる枚数が多くない場合は、スライドバーファイルを使用した保管方法もおすすめです。
スライドバーファイルとは、綴じ具をスライドして書類を綴じることができるクリアファイルです。
100均やネット通販などで購入することができます。
手順としては、クリアファイルに書類を入れて綴じ具を上から下にスライドさせるだけで完成です。
しかし、綴じる枚数が少ない場合はスライドバーが外れてしまう可能性もあります。
その場合は、スライドバーは使わずにクリップでとめると良いかもしれません。
クリアファイルなので書類の内容も分かりやすく、そのままページもめくれるので便利です。
ルーズリーフの長期保管方法は製本がおすすめ!
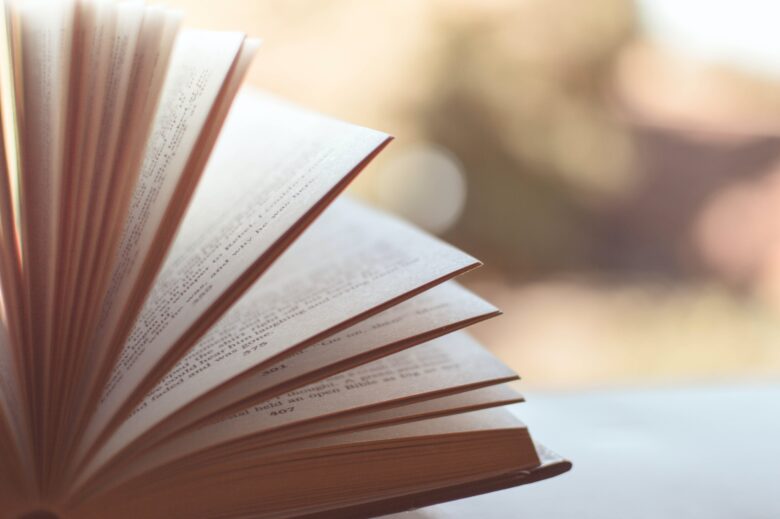
使い終わったルーズリーフを長期で保管しておきたいという場合のおすすめの保管方法は、製本です。
ルーズリーフを本のように、ひもで綴じて製本する保管方法です。

でも製本って時間がかかるんでしょ?
確かに慣れるまでは時間がかかるかもしれません。
しかし、慣れると5分〜10分すぐに終わってしまうほど簡単に作業することができます。
また、準備する材料はタコ糸とひも通しのみで十分です。
タコ糸やひも通しは100均で揃えることができるので、コスパの良い保管方法と言えます。
製本の手順を簡単に説明すると、ひも通しにタコ糸を通してルーズリーフの穴を縫っていくという工程で、非常にシンプルです。
もっとオシャレに保管したいという方は、マスキングテープやリボンなどを使ってみるのがおすすめです。
背表紙にマスキングテープを貼り、タコ糸の代わりにリボンを使えばオシャレに製本することができます!
ルーズリーフの詳しい製本方法はYouTubeで見ることができますので、気になる方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
まとめ

- 使用前のルーズリーフの保管方法は、ルーズリーフケース、クリアファイル、クリップボードがおすすめ
- 使用後のルーズリーフの保管方法は、定番のバインダー以外に、ペーパーファスナー、封筒、ルーズリーフリング、スライドバーファイルで保管する方法がある
- 使用後のルーズリーフを長期保管する場合は製本がおすすめ
クリアファイルや封筒を使用すれば、リーズナブルにルーズリーフを保管することができます。
ルーズリーフを長期保管する場合は製本がおすすめですが、慣れるまでは時間がかかります。
しかし慣れてしまえば数分で作業することが可能なので、おすすめです。
また、マスキングテープやリボンを使うことでオシャレに製本することができます。
自分の用途に合ったルーズリーフの保管方法を見つけ、ストレスとおさらばしましょう!
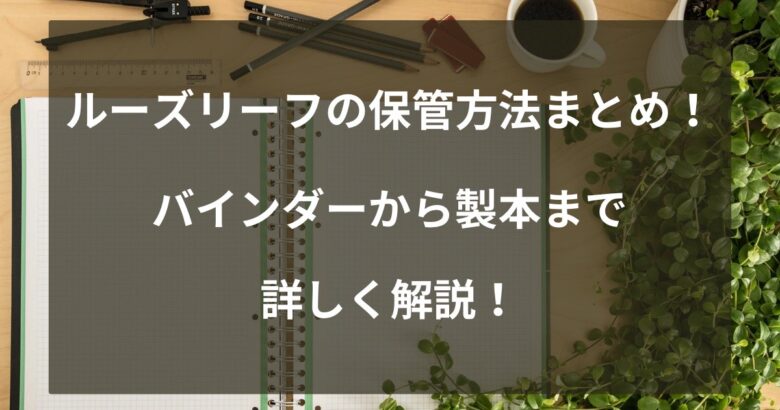

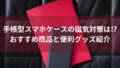

コメント