
もうすぐ子供が大学生になるかもしれないけど、お金ってどこまで親が払うの?

どこまでが平均?親としてちゃんと払いたいけど、金額が高かったら少し心配…。
進路の変更も必要なのかも?

親が払うとしてもどんな事を決めればいい?大学生って実際には何が必要?
どんなことにお金をかけてるの?
この記事を読まれている方の中には、上記の様なお悩みがあるかもしれません。
親としてはどこまで払うか、しっかり分かってから対策はしたいもの。
その一方で、「子供の夢や、大学生としての生活もお金が原因で諦めて欲しくない!」という気持ちもありますよね。
そんな方のために、今回は大学生に対してどこまで親が払うのかの基本的な考え方や、実際の学費、アルバイトについて紹介していきます。
ご家庭によって事情は異なると思いますが、ぜひ参考にしてみてください!
大学生に対してどこまで親が払う?平均と基本的な考え方は?

大学生の費用に関しては、親がどこまで払うのがいいのか決めることはなかなか大変ですよね。
そのためここでは、まず平均的にどこまで親が支払っているかを紹介します。
基本的にどうしたらいいのか迷っている方は、その平均を参考にしてみてください。
その後、大学生の子供に対してどこまで親が払うのかに対して、決めるための基本的な考え方についてお伝えします!
平均と決めるための考え方を参考に、素敵な進路を歩んでくださいね!
大学生にどこまで親が出してる?よくある意見は?
まずは、みなさんどこまで大学生のお子さんに、お金を支払っているのでしょうか?
少し調べてみましたが、親が払うことが一番多かった費用としては、学費、教科書代、交通費(普段大学へ通う際の費用)が挙げられます。
特に親世代と異なる出費として注目するは、大学生でもパソコンが必須になっていること。
レポート、卒論の作成、発表資料の作成の際に必ず必要となるので、入学の際に購入を求められます。
意外と費用が掛かるので、注意が必要です。
反対に大学生のお子さんが払うもので多かったのは、サークルなどへの参加費用、遊ぶための費用(旅行も含む)、食費、洋服代などが挙げられます。
まとめると全体的な傾向としては、大きな出費、なおかつ、必ず払う、そして金額が分かっている費用を親が払うという形が多いです。
その一方で、その場合はかかる金額を工夫できる出費(遊ぶお金や電話代、洋服代など)は大学生の子どもが払うと取り決めている様ですね。
もし、どこから決めていいのか分からないという方は、この形から初めてみてもいいのではないでしょうか?
大学生活の中で様子を見ながら変更することもできるので、スタートをそこに設定してみることをオススメします!
ちなみに私の周りでも、このケースが一番多かったですね。
親が学費などの大きな費用を払うことが難しい場合、心配な場合は奨学金をそこに使うという形でした。
親がどこまで払うかの基本的な考え方とは?
それでは平均は分かったとして、どの様に項目や詳細を考えていったらいいのでしょうか?
まず結論として、どこまで親が学費を払うのか、どこまで負担するのかに関して、正確な金額や正解はありません。
様々なところで言われているように、それは各々の家庭が置かれた状況もありますし、負担できる金額もそれによって変わってくるためです。
また、奨学金を借りることもあるかもしれませんが、その金額もご家庭によって様々です。
そのため、これから紹介する考え方をもとにして、お子さんとよく話し合ってみることが大切です。
お互いに納得した上で、戦略的に進路を組み立てて行きましょう!
考え方としては、大きく分けて下記の3つの視点が挙げられます。
- (本当に)何のために大学に行くのか
- 子供が生活していきたい環境/親が生活してほしい環境とは何なのか
- 子供が自立する範囲とはどこまでなのか
では、それぞれ細かく見ていきましょう。
〈何のために大学に行くのか?〉
1つ目の観点については、子供にとって一見するとわかりやすい観点のように見えます。
あるいは、ありきたりでちょっと哲学的な問いかもしれません。
そう感じる理由としては、これは大学や学科を選ぶ際に、様々な方面(学校や親、塾の先生や友達など)から、なんとなくふわっとした雰囲気でよく問われる質問だからです。
しかし、「(本当に)何のために大学に行くのか」を、偏差値や学費、周りの学生の様子などの要素を抜いたところで、真剣に親と話し合う機会はどれくらいあるのでしょうか?
最近ではこうした話し合いは少なくなっているのではないかと、数年前に大学生だった私は同級生を見てきて感じています。
例えば子供が「こんな勉強がこれくらいしたい!」と本気で考えていれば、親も「これくらい出したい!」と思うことがあるかもしれません。
また、子供が「もっと遊びも含めて、こんなことをしたい!」という場合であれば、「それは分かるけど、遊びやこの部分は自分で出してね」と話すこともあるかもしれません。
どちらの選択も正しいですし、両方が合意していればそれに向けて各々が努力し、協力することが出来ます。
ちなみに私の場合は、理想の大学生活を送れそうな条件を全部ピックアップして、「それができるこの大学しか受けないので、援助をお願いします!」と親に宣言しました(笑)
そのあとかかる金額を算出して、これくらい欲しいという金額もしっかり出して、親に受け入れてもらうことが出来ました。
現在多くの家庭では大学での費用が教育の中で一番大きな出費になることがある一方で、子供がそれを分かっていない、あるいは十分に理解していない場合があります。
あるいは反対に、子供が遠慮しすぎて話し合いもなく、納得できない進路を歩んでしまうこともあります。
そのため、本当に何を考えているのかや、どんなことをしたいのかを深堀していき、両者で折り合いをつけていくことはお互いのためにとても大切です。
せっかく行くのであれば、ちゃんと応援したいものですしね!
こうした両方の理解が必要となる流れは、昔と異なり、大学に行くことが当たり前になりつつあることも背景にあります。
「みんな行っているから…。」や「行かないと就職に響いちゃうじゃん…。とにかくどこでも行く!」ということがどうしても先行してしまうからです。
そういう意味では、最近では意外と見過ごされやすい観点です。
もし高校生や中学生のお子さんを持たれている方は、普段からこうした観点でも会話をしてみるといいのかもしれません。
〈子供が生活していきたい環境/親が生活してほしい環境とは何なのか〉
こちらも大学生活の費用をどこまで親が払うかを考えたときは、必要な観点です。
ここの環境とは、大きく分けると家を出ていくのか、実家から通うのかなどを指しています。
一概に言うことはできませんが、下記のようなことは、合格後の大学によっても少し変わってくるのではないでしょうか?

国公立大学であれば、費用の負担ができるから家から出てもいい!

私立なら家から通わないと、学費以外を払うのは難しい…。
そのため、大学受験を前にどんな大学に行ったら、どんな環境になるかのシュミレーションを行っておくこと、そして話し合っておくことが大切です。
「国公立なら」や「私立なら」、「東京で住むなら」や「家から出るなら」など、大まかな想定でも問題ありません。
「ここに行ったら一人暮らしすることになるけど、どれくらい必要になると思う?」や、「実家にいても、何にどれくらいかかると思う?」などの質問形式で話してみましょう。
この時に注意するのは、親は「こちらが払うんだから」という圧力をかけすぎてしまわないこと。
金額のことはありますが、基本的には一緒に考えていくスタンスが大切です。
もちろん、子供にとっては初めてのこともあるので、はっきりした答えはすぐに出ないこともあります。
しかし、こうしたシュミレーションを何回か行うことを通して、子供にとって自分には何が必要なのか考えるきっかけとなります。
そして、お金のことを可視化できる良い機会ともなります。
こうした話し合いは、子供本人の意欲や受験時のモチベーションにもつながる可能性もあるので、機会があれば少し話し合ってみてもいいのではないでしょうか。
〈子供が自立する範囲とはどこまでなのか〉
こちらはお金のことのみに関わらず、生活全般に関しても共通する観点なのかもしれません。
大学生になれば、バイトや授業、課外学習やサークル、その他研修なども含めて、子供が出会う人の数は高校時代と比べても圧倒的に広がります。
そうした人たちと付き合いながら、社会の中で親を介さずうまくやっていくことも、大学生活の中では大切な要素となります。
しかし、親御さんとしては心配な面もありますよね。
特に付き合いや旅行で高額なお金がかかると言われた時には、その理由が気になってしまったり、一緒に暮らしていても見えない範囲が出てくることもあります。
また、一人暮らしで生きていく場合は、生活の面でも親御さんの手を離れることになるので、親としては余計不安にもなります。
もしくは頑張るタイプのお子さんの場合、お金を稼ぐことが先行しすぎてしまい、アルバイトと学業のバランスがくずれてしまうこともあります。
そのため、下記の要素はあらかじめはなしておくことが大切です。
- どんな生活を送っていくのか
- 大きな金額を払うと想定できるのはどんな時か
- 金額としてどこまでであれば、子供が自分で出すのか
- どんな用途であれば親が追加で出すこともあるのか など…
あらかじめ想定できることを両者で相談しておけば、子供の側も「親はこんなことに不安を感じるのか!」と知る機会にもなります。
大切なのは生活の面も含めて、信頼して一緒に考えるという姿勢を見せること。
少しでも不安を解消した状態で、お子さんの進学に向けて準備していきましょう!
以上が大学生に対して、どこまで親が払うのか考える際の基本的な観点となります。
この考え方をもとにして、お子さんと日々少しずつ話し合ってみてください。
こうした話し合いをすることで、お互いが納得しながら、どこまで奨学金で補うのか、子供自身がどこまで払うのか、親はどこまで払うのかなどの部分が明確となります。
少しでも理解を進めたうえで素敵な進路を選ぶことが出来るといいですね!
大学生へどこまで学費を負担してる?他の費用や仕送りについても!

それでは実際に、大学生の大学生活にかかる費用に関して、どれくらい親がお金を払っているのでしょうか?
ここからは一番費用がかかる、「学費」を中心に、そのほかの費用(生活費や仕送りなど)も合わせて3点から統計的な数値を見ていきたいと思います。
上記の基本的な観点を、お子さんと話す際の材料にしてみてくださいね!
- 学費ってどれくらいかかる?
- 生活費の考え方は?
- 仕送りってどこまで出しているの?
学費ってどれくらいかかるの?
まず、大学生活の中で一番大きな出費となるのは、学費。
こちらは国公立と私立、学科などでも大きな違いがあります。
また、留学などを希望している場合は、別途その分費用が掛かる可能性もあります。
ただ、大学によっては日本の大学に学費を納めれば、留学先の学費は免除されるなどの交換留学制度もあるので、大学によってさまざまです。
実際私も留学を希望していたので、交換留学制度のある大学を選んで受験し、留学しました。
そうしたことも含めて、大学の制度、学費の仕組みも調べておくことをおススメします。
ちなみに、文部科学省の調査によると、国公立と私立大学の学費は下記の通りになります。
令和元年のデータではありますが、基本的にはそこまで大きく変わってはいませんので、参考になるかと思います!
| 国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | |
| 授業料 | 535,800 | 536,328 | 911,716 |
| 入学料 | 282,000 | 392,391 | 248,813 |
| 施設設備費 | なし | なし | 150,000 |
| 4年間在学した際の費用 | 2,425,200 | 2,537,703 | 4,495,677 |
公立大学と私立大学は、各々大学で入学料、授業料が異なるためここでは平均の金額を算出しています。
また、ここでは公立大学の入学料が高く感じられますが、これは地域外の生徒が入学してくる場合で金額を算出しているためです。
公立大学ごとに地域は異なりますが、地域内から通うことを考えればこれより費用は下がる可能性があります。
さてここからは、大まかな学費の金額を見ていきましょう。
授業料と入学料を合計すると、国公立大学であれば250万円、私立大学であれば390万円ほどが必要になることが分かります。
私立大学ではこれに加えて、施設設備費がかかってくることに注意が必要です。
こちらは学部によっても変わってきますが、文系の場合は年間15万円、理系の学部であれば、年間18万円ほどとされています。
医学部などに関しては、大学の施設をより使用することになるので、年間100万円と高額になります。
上記の表は文系の学生の場合で換算しているので、施設設備費を学費に加えると約450万円ほどが合計で必要です。
この辺りは進路を考える際に、必要なデータとなります。
お子さんの意欲に合わせて様々なパターンを想定しておくのがいいのかもしれません。
生活費の考え方は?
生活費に関しては、実家に住む場合はほとんどかかることがありません。
もしかかってくる費用があるとすれば、交通費と電話代、交際費くらいでしょうか?
そのため、ここでは一人暮らしをするためにかかる金額を試算してみました。
大学生でどれくらいかかるのか、参考にしてみてください。
まず、生活費の内訳と金額は、全国大学生活協同組合連合会によると大きく分けて下記の通りで表すことができます。
| 必要項目 | 首都圏 | 首都圏以外 | 全国平均の金額 |
| 家賃 | 66,170 | 約49,000 | 53,920 |
| 食費 | 27,430 | 約23,000 | 24,680 |
| 交通費 | 6,120 | 約3,000 | 3,850 |
| 教養娯楽費 | 13,460 | 約11,000 | 11,760 |
| 書籍費 | 2,190 | 約1,000 | 1,700 |
| 勉学費 | 1,910 | 約2,000 | 1,900 |
| 日常費 | 8,080 | 約7,000 | 7,520 |
| 電話代 | 3,800 | 約3,000 | 3,110 |
| その他 | 2,520 | 約2,000 | 2,310 |
| 貯金・繰越 | 11,380 | 約14,000 | 14,300 |
| 合計 | 143,060 | 約115,000 | 125,050 |
大体合計としては、12万円から15万円ほどの間に収まりそうです。
この中で親としてどれくらいお金を払うのか、少しでも調整できるものとしては、家賃が一番なのではないでしょうか?
一番出費がかさむ分、ここを少し抑えれば、年間を通して大きな節約になります。
家賃に関して心配な場合はオープンキャンパスなど、大学の近くに寄る際に、大学周辺の不動産物件を見ておくこともおすすめします。
ちなみに私の場合は、国公立大学で1年時は全寮制だったため家賃は破格の1万5千円。
受験後も物件を探す手間が省けましたし、親としてはものすごく助かったかもしれません。
2年生からは友人とルームシェアしていたので、家賃と高熱費を合わせて3万円のところに移り住みました。
それでも、他の友人たちと比べると安かったかもしれません。
ちなみに留学時も、家賃をそのまま払い続けて、荷物を部屋にキープしてもらっていました。
家具を実家に送ったり、コンテナを借りて荷物を預けるよりも、その方が安かったからです!
留学した私の周りの友人たちもその方法は使っていたので、住む土地によっては有効な方法だと思います。
どうしても家賃を抑えたい場合は、大学の寮やルームシェアなども検討してみてもいいのかもしれませんね。
家賃以外の生活費で出費を抑える際はさまざまな工夫がありますが、最近は格安SIMなどが出ているので、電話代なども安く抑えることが比較的簡単です。
他にも光熱費の見直しを継続的におこなっていったり、中古の教科書を買う、譲り受けることで教科書代も浮かすなどのこともできます。く
上記のデータを参考に大型の出費は親が払う、それ以外は大学生の子供が払う、などの分担を決めていくとやりやすいのではないでしょうか?
色々なデータを集めて想定し、話し合ってみましょう!
仕送りってどこまで出しているの?
仕送りについてもどこまで親が出しているのか、見ていきましょう。
全国大学生活協同組合連合会のデータによれば、仕送りの平均は71,880円。
大都市圏なども含めて下記の通りにまとめてみました。
| 首都圏 | 首都圏以外 | 全国平均 | |
| 仕送り | 85,630 | 約63,000 | 71,880 |
こちらもご家庭の事情、また生活する土地にもよりますが、平均値ではあるので参考にはなるかと思います。
ちなみに私の場合は、福岡の大学に進学し大学1年時は全寮制だったので、大学1年生の時とそれ以降では仕送りの金額は異なっていました。
大学1年時は7万、2年生から8万ほどだったと思います。
ちなみにこの金額には、家賃も含んでいます。
仕送りのことを考える時に気になるのは、上記でも紹介した生活費のやりくり。
生活費に関しては、お子さん本人の工夫次第で抑えることができます。
仕送りの金額を一緒に考える時には、そうした工夫も伝えるといいのかもしれませんね。
どこが削れるのか、逆に何を大切にするべきなのかを明らかにした上で、お子さんと話し合って決めてみてください。
大学生がどこまでアルバイトで稼げるのかも考えてみよう

ここまでは、大学生に対して親がどこまで払うのか、その考え方と費用に関して考えてきました。
ご家庭によっては、大学生活にかかる費用の全てを払うのはなかなか難しいところもあるのではないでしょうか?
そうしたことから候補に上がってくるのは、大学生であるお子さんがアルバイトして、費用を稼ぐということ。
そのためここからはそれを踏まえて、大学生がお金を稼ぐ手段としてのアルバイトに着目して紹介していきます。
アルバイトに関しては、大きく分けて下記の2点について述べていきたいと思います。
- 稼げるアルバイトってどんなもの?
- 学生でアルバイトをする際に気をつけることは?
稼げるアルバイトってどんなもの?
独立行政法人日本学生支援機構の調査によると、大学生がアルバイトで稼ぐことができる年収は約40万円ほど、平均して毎月3万3千円と言われています。
平均が上記の金額なので、それよりも上回る金額を稼ぐアルバイトをここでは「稼げる」として、その選び方を紹介していきます。
稼げるアルバイトには下記の様な条件があります。
- 深夜か早朝のアルバイトを選ぶ
- 時間に関係なく時給が高いアルバイトを選ぶ
深夜か早朝のアルバイトに関しては、夜間手当がつくことがあるので、ある時間帯になると時給が比較的高くなることがあります。
体力に自信があって、どこまで稼ぎたいのか金額が目標として決まっている場合は、一定期間働くことはいいのかもしれません。
また、シフトの数を調整できるのであれば、一週間で働く数を少なくして、継続的に働いて一定の金額を稼ぐことも可能です。
種類としては、早朝の新聞配達や工場の夜勤勤務、ホテルのフロントなどのサービス業、コンビニの深夜勤務などがあります。
また時間に関係なく時給の高いアルバイトに関しては、専門性が求められる仕事が多いことがあります。
例えば、家庭教師やコールセンターなどが挙げられます。
こちらはコミュニケーションや電話対応など社会に出て役に立つことも学べるので、就職のことを見据えて働いてみることもありかもしれません。
また、歩合制の場合もあるので、本人の能力次第でどこまでも稼ぐことのできる可能性もあります。
どちらにせよ、学業と両立しながらできそうな、お子さんにあったアルバイトを探してみるようアドバイスされてくださいね!
ちなみに実は私も大学生の時、24時間開いているホテルのフロントスタッフや、物流倉庫での早朝仕分けのスタッフとして、アルバイトをしていたことがありました。
留学の生活費や就活費用を稼ぐために始めたアルバイトでしたが、今振り返れば学業とアルバイトを両立させるために、スケジュールをやりくりする力が身についたと思います。
例えば、ホテルのアルバイトのスケジュールでは、平日に大学に通い課題を終わらせ、金曜日の夜から土曜日の朝、土曜日の夜から日曜日の朝まで働くというものでした。
この方法だと週に2日間の勤務で、月8万円ほどを稼ぐことができたので、体力的にも無理なく働くことができました。
ちなみに半年間週末を使って働いたため、おかげで遊ぶ時間はあまりありませんでしたが…笑
それなりの金額を稼ぎたい、あるいは必要だという場合は、上記の様なアルバイトを基準に考えてみてもいいのかもしれません。
学生でアルバイトをする際に気をつけることは?
ただ学生でアルバイトを行う場合には、気をつけることもあります。
それは「103万円の壁」。
詳しく説明すると、「103万円の壁」とは年間で103万円以上稼いでしまうと新たに税金が課税されてしまうことを指します。
もし、103万円以上稼いでしまうと、大学生のお子さん本人に所得税、親御さんには扶養控除額に住民税と所得税の両方が掛かってしまいます。
歩合制の仕事は「どこまでも稼ぐことのできる」と先ほど紹介していますが、実質的にはこの金額を超えてしまうことには注意が必要です。
ちなみにアルバイトを何個か掛け持ちしている場合は、合算された金額で103万円を超えないか確認が必要です。
せっかくが頑張って稼いだのに追加で税金がかかってしまうのは、なんだか残念ですよね。
そのため余程の事情がなければ、103万円以上稼ぐことは避ける様にしたほうが無難です。
お子さんが働いて学費や生活費の一部を払う場合は、こうしたことにも気を配る必要があります。
まとめ
- 大学生にどこまで親が払うのかには正解はない!
- どこまで払うかは親と子供の両方が納得することが大事
- なんのために大学に行くのかも、どれくらい親が払うかの指針になる
- 環境や大学生の自立に関しても着目して話し合ってみて!
- どこまで親が払うのかは、学費や生活費の平均も参考に考えることができる!
- 大学生がアルバイトでどこまで生活費を賄えるかも参考に!
みなさん、いかがだったでしょうか?
「大学時代こんな感じだったなぁ〜」と思い出しながら、思わず色々と書いてしまったのですが、皆さんの参考になったら嬉しいです!
ちなみに受験の直前でこうしたことを決めていくのは大変だと思うので、理想は高校1年生から少しずつお子さんと話し合いができるといいと思います。
みなさんにとって大切な決断にもなるので、納得のいく進路に進めるといいですね。
陰ながら応援しております!
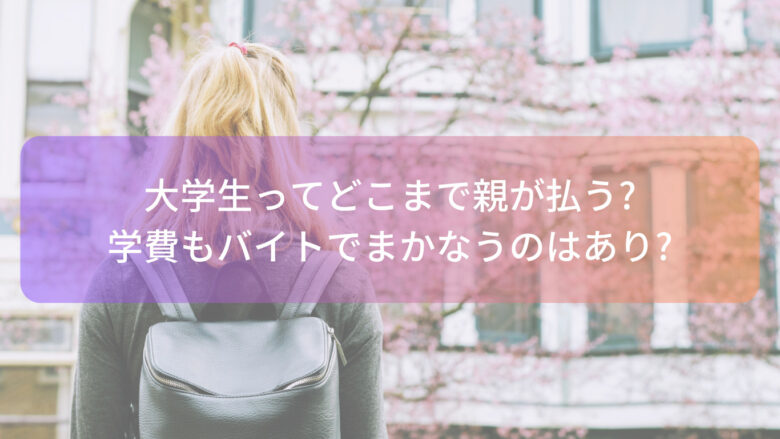


コメント