働いた証となる給与明細ですが、あなたは給与明細を保管していますか?
給与明細は、収入の証明や年金の支払額の証明などに使用することができ、いざという時にあなたを守ってくれる存在になります。

でも、給与明細ってどのように保管するのがおすすめなの?
給与明細といっても、紙なのかデータなのかは人それぞれで、何年保管しておけば良いのかも疑問ですよね!
しかし、そもそも何のために給与明細を保管するのかという理由が分かっていなければ、このような悩みは永遠と続きます。
そこで今回は、以下の内容を解説していきます。
- 給与明細のおすすめな保管方法
- 給与明細を保管する理由
- 紙ベースの保管方法に便利なダイソーや無印良品グッズ4点紹介
この記事を読めば、あなたに合った給与明細の保管方法が見つかるはずです!
給与明細の保管方法おすすめ紹介!紙とデータでの保管方法の比較

給与明細は、働いている企業によって発行の仕方が違います。
以前は、給与明細を紙で発行する会社がほとんどでした。
私も社会人になってすぐの頃は、給与明細の入った封筒を貰うたびに給料日を実感して感動した記憶があります!
しかしペーパーレス化が進む現代では、給与明細をオンライン上で発行する企業が増えてきました。
そして、給与明細を紙で保管する人とデータで保管する人で分かれているのが現状です!
もしくは、額面だけ確認して給与明細を保管していない方もいるかもしれません。
データでの保管には、紛失するリスクが低いことや場所を取らないというメリットがあります。
紙で保管する場合、少量であれば問題なくても、そこそこの量を保管しようと思うと紙がかさばって場所をとりますよね!
また、紙の給与明細の場合、きちんと整理していないと、探したい期間の明細がすぐに見つからずに手間がかかる可能性もあります。
私も以前は給与明細を紙ベースで保管していましたが、途中でファイリングが面倒になって保管が煩雑になってしまいました。
その結果、いざ必要なときに見つからず、苦労したという経験があります。
しかし、紙ベースでの保管方法の方が安心できるという方も多いのではないでしょうか?
紙ベースでの保管に慣れているという方やインターネットが苦手な方には、紙ベースでの保管方法の方が向いているでしょう。

私にはどっちの保管方法が向いているんだろう…
こんなふうに思っている方も、安心してください。
これから、それぞれのおすすめな保管方法をご紹介します。
どちらかを実践してみるのも良いですし、直近の給与明細だけ紙ベースで保管しておき、残りは破棄してデータベースで保管するという方法もおすすめです。
それぞれ比較しながら、あなたに合った保管方法を見つけてみてくださいね!
紙ベースでおすすめの保管方法
紙の状態で給与明細を保管する場合は、仕切り付きのファイルを使用するのが最もおすすめです。
上から入れるだけなので、ノートに貼ったり、穴を開けてファイリングするよりも手間がかかりません。
また、仕切りがあることによって、期間別に分けたり、給与明細と源泉徴収票を分けて保管したりすることができます。
他にも、タグの付いたファイルをボックスに入れて保管したり、インデックスシールなどを活用してファイルで保管するという方法もあります。
パッと見ただけで、いつの給与明細なのかが分かるように保管するのがポイントです!
この保管方法であれば、いざというときでも、探したい時期の給与明細をすぐに見つけることができるでしょう!
データベースでおすすめの保管方法
毎月の給与明細を紙で貰っている方でも、データベースで保管することは可能です。
スマホのスキャンアプリを使用すると、給与明細を撮影するだけでPDFの状態にすることができ、簡単にデータ化することができます。
PDFとは「Portable Document Format(ポータブル・ドキュメント・フォーマット)」の略で、Adobe(アドビ)が開発したファイル形式です。
PDFは文書を紙に印刷したときと同じレイアウトで保存でき、PCやスマホなど、どんな環境で開いても基本的に同じように表示できるのが特長です。
文書をパスワードで保護でき、印刷代や紙代の削減にもつながるので、契約書類やマニュアルなど、様々な文書に採用されています。
引用 Adobe
もともと、毎月の給与明細をデータベースで貰っている方は、そのままダウンロードして自分のフォルダに保管するだけで済むので簡単です!
フォルダに保存する場合は、タイトルを支給日などの分かりやすい名称にしておくのがおすすめです!
給与明細の保管方法が役立つ理由と保管年数

そもそも、給与明細はなぜ保管しておく必要があるのでしょうか?
その理由を簡単に説明すると、自分の身を守るために必要だからです!
給与明細は主に以下のような場合に役立ちます。
- 収入の証明
- 確定申告をする際の源泉徴収票の代わり
- 税金や年金の支払いの証明
- 雇用保険による失業給付金を受ける際、離職票の金額の照合
- ローンや賃貸の審査を受ける際の直近の収入の証明
- 企業による未払金の請求の際の証拠
手違いで、給与明細の金額よりも少ない金額が振り込まれたということは、珍しい話ではありません。
しばらく経って気づいたとしても、手遅れになってしまう可能性もあります。
給与明細がデータベースで発行されている場合は、過去の給与明細がデータで確認できたり、印刷したりできることが多いです。
しかし、給与明細が紙ベースで発行されている場合、そう簡単ではありません。
企業には、給与明細の再発行の義務はないので、再発行してくれない可能性があるのです。
また、給与明細を全く保管せずに何らかのトラブルがあった場合、過去の収入を証明できるものがないと不利になります。
そんな不測の事態に備えるためにも、給与明細は大切に保管しておくことがおすすめです。
リスクに備えて給与明細を保管する年数

一体、何年分を保管しておけばいいの?
給与明細は最低でも5年は保管しておくのがおすすめです。
現在の給料の未払い金が請求できる時効は3年ですが、今後5年に延びる可能性が高いです。
また、雇用保険による失業給付の請求時効は2年なので、最低でも5年分保管しておけばリスクに備えることができます。
このように、何の目的で給与明細を保管するのかという理由によって、保管方法や保管期間は変わってきます。
例えば、不測の事態に備えるために、全ての給与明細を保管したいと思った場合を想像してみてください。
紙の状態での保管方法だと場所がいくらあっても足りないので、このような場合はデータでの保管方法の方が向いています。
最低限のリスクに備えるために、数年分だけ給与明細を保管したいという場合は、紙の状態での保管方法でも良いでしょう。
あなたも、まずはどんな目的で給与明細を保管するのかという理由を考えて、保管方法を考えてみましょう!
給与明細の紙での保管方法はダイソーや無印良品のグッズを使用すると便利!
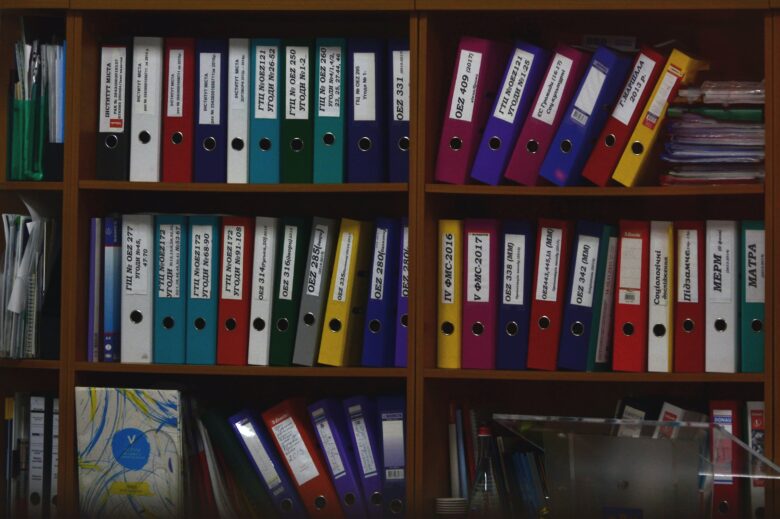
給与明細を紙ベースで保管する場合は、ダイソーや無印良品のグッズを使用した保管方法がおすすめです。
あまりお金をかけずに整理したい場合や、保管する量が多い場合はダイソーのグッズを使用するのが良いでしょう。
素材や使いやすさを重視するなら、無印良品のグッズをおすすめします。
ここからは、ダイソーや無印良品で購入できる、給与明細を保管するのに便利な商品をご紹介していきます!
ダイソー:セクションファイル(仕切り付、6ポケット)

引用 ダイソーネットストア
この商品は、上から簡単に書類を入れることができ、ポケットも6つ付いています。
仕切りがあるため、期間や種類ごとに分けることができて便利なファイルです。
値段も安いので、いくつか購入し、期間に分けてファイリングするのもおすすめです。
中の内容が分かりやすいように、ファイルの表面にタイトルを書いたシールを貼ると良いですね!
シールの代わりにマスキングテープを使用して、その上にタイトルを書くと可愛くなります!
ダイソー:A4フラットファイル

引用 ダイソーネットストア
ダイソーのフラットファイルも、給与明細の保管に便利です。
今回はA4の横長なタイプを紹介していますが、縦長のものやサイズ違いのものもあります。
色違いも売っていますので、種類によって色を分ける保管方法も良いでしょう。
また、インデックスシールを活用することにより、同じファイルでも分別して保管することができます。
無印良品:個別フォルダ

引用 無印良品
こちらの個別フォルダは、無印良品で購入することができます。
素材がしっかりしており、折れ曲がる心配もありません。
ラベルを貼る場所も付いているので、分別管理がしやすいのがポイントです!
別売りのペーパーファスナーを使用して、書類をしっかり綴じることも可能です。
シックな色なので、家の雰囲気を崩すこともなくて良いですね!
無印良品:ファイルボックス

引用 無印良品
こちらの無印良品のファイルボックスは、1つ前に紹介した個別フォルダを入れて管理するのがおすすめです。
個別フォルダをまとめて保管することができて、給与明細をまとめて保管することができます。
また、ラベルも見やすいので、パッと見ただけで中身が分かる保管方法です。
すぐに取り出すことができるのもメリットの1つです!
まとめ

- 少量の保管や、紙の状態の保管に慣れている方は、紙ベースでの保管方法がおすすめ
- 大量の保管や、そもそも給与明細がデータベースで発行されている方は、データベースでの保管方法がおすすめ
- 不測の事態から自分の身を守るためにも、給与明細を保管しよう
- 給与明細を紙の状態で保管するなら、仕切り付きファイルを使用するのがおすすめ
- 紙の給与明細を保管する際は、ダイソーや無印良品のグッズを活用すると便利
給与明細を紙ベースで貰っているという方でも、スキャンアプリで写真を撮るだけでデータ化することができます。
まずは給与明細を保管する目的から考えて、それから目的に合った保管方法を選ぶのがおすすめです。
給与明細を紙の状態で保管する場合は、パッと見ただけで中身が分かるように保管するのがポイントです!
自分にピッタリの保管方法を見つけて、今日からストレスとおさらばしましょう!
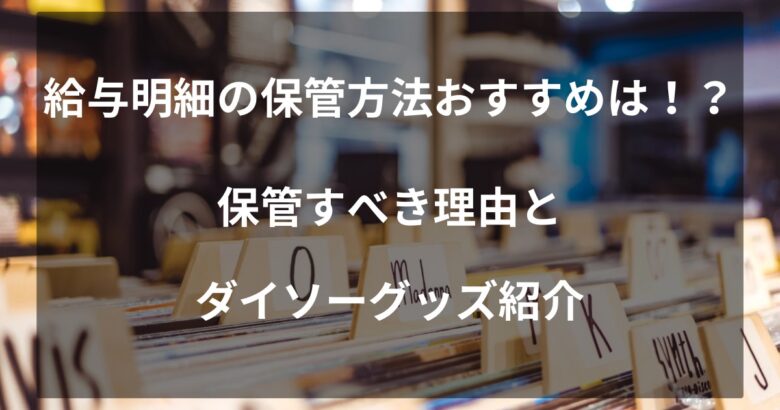

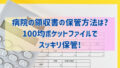
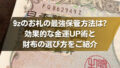
コメント